
朝の満員電車、押しつぶされるような車内でスマホを眺めていたら、隣の上司がLINEで「今日の会議、また遅れるなよ」とメッセージを送ってきた。
毎日顔を合わせる上司なのに、何気ない言葉にもイラッとしてしまう。会議中も細かい指摘ばかり。やってられない…と思いながらも、表面上は「了解しました」と笑顔で返す。
あなたにも、そんな“なんとなく苦手”な人がいませんか?
実はその「苦手」という感情、相手の性格や態度が原因ではなく、“自分自身の認知のクセ”から生まれているのかもしれません。
「苦手な人」はあなたの中にいる?

本書『苦手な人と上手につきあう技術』(伊庭正康 著)は、ただのハウツー本ではありません。
営業のプロフェッショナルである著者が、数千人と向き合ってきた中で培った“対人スキル”を体系化し、苦手な人との関係を根本から変える「認知行動×相性理論」を紹介しています。
著者が強調するのは、苦手な人のせいにするのではなく「自分の評価の仕方=認知の歪み」に目を向けること。
たとえば、いつも時間通りに行動するあなたが、毎回10分遅れてくる同僚にイライラしてしまうのは、「時間は守るべきだ」という“べき思考”が根本にあるから。
逆に、自分のミスを必要以上에 자책하는人は、「失敗=無能」という“マイナス思考”に支配されているのかもしれません。
認知の歪みを整える「セルフトーク」とは?

たとえば、あなたが「またあの人にムカついた…」と思ったとき、そのイライラの裏には「~であるべき」という固定観念が潜んでいるかもしれません。
本書では、こうした無意識の思考パターン、つまり“認知の歪み”に気づくことが大切だと説きます。
そこで役立つのが「セルフトーク(心の中のひとりごと)」です。
これは、瞬間的に浮かぶ感情や判断に対して、自分自身が冷静につっこみを入れる思考法です。
たとえば「上司の言い方、マジでムカつく!」という自動思考が湧いたとき、「本当に“いつも”そうだろうか?」と問い直してみる。
このように一呼吸おいて考えるだけで、感情の暴走にブレーキがかかり、客観的な視点が戻ってきます。
「べき思考」が強い人には、「人には人のやり方があるよね」「それもアリかも」と言い聞かせるだけで心が軽くなるでしょう。
「マイナス思考」の傾向がある人なら、「できないことが多い=まだ伸びしろがある」とポジティブに転換するセルフトークが効果的です。
大事なのは、自分に合ったフレーズをあらかじめいくつか用意しておき、心が揺れた瞬間に使えるようトレーニングしておくことです。
好きな漫画のセリフや名言をアレンジしてもOK。心の中の「もうひとりの自分」を育てることが、対人ストレスを減らす第一歩になります。
相手を“人”ではなく“タイプ”として見る「相性マトリクス」

さらに、著者が開発した「相性マトリクス」を使えば、苦手な相手を“人格”ではなく“タイプ”として分類し、合理的に対処できるようになります。
4つのタイプ
| タイプ | 特徴 | 認識のポイント |
|---|---|---|
| 独裁タイプ(ドライビング) | 結果重視、せっかち | メリットを重視して提案を |
| 感覚タイプ(エクスプレッシブ) | ノリ重視、アイデアマン | 共感と盛り上げで心を掴む |
| 理屈タイプ(アナリティカル) | ロジカル、慎重 | 論理とデータで安心を |
| 迎合タイプ(エミアブル) | 協調重視、平和志向 | 丁寧な配慮と傾聴が鍵 |
たとえば、冷たく見える「独裁タイプ」には「それって効率的ですね!」と相手の価値観に乗っかって話すと、一気に関係が和らぐことも。
逆に、自分が「マイナス思考」の傾向にある場合は、「相手がすごい=自分がダメ」ではなく、「相手と自分は違うだけ」と線引きをするだけでも、関係が劇的に改善します。
苦手な人が「強力な味方」になる日
著者は「初対面で苦手な人でも、10回は会ってみる」と言います。
回数を重ねるうちに見えてくる相手の“スタイル”さえ掴めば、その人との距離感を自在に調整できるようになるからです。
実際、会社でも家庭でも、「絶対に苦手!」と思っていた人が、ちょっとした視点の転換で“理解できる存在”に変わる瞬間があります。
結論:「苦手な人」と付き合える人は、人生の選択肢が広がる

「苦手な人」と距離を置くだけでは、根本的な解決にはなりません。
むしろ、そうした人とうまく付き合える人こそが、職場でも私生活でも信頼を集める存在です。
この本は、そんな人間関係の達人になるための“ガイドブック”。
- あの上司ともっと冷静に話せるようになりたい
- 顧客との関係を改善したい
- 義理の家族とのストレスを減らしたい
そう感じているあなたにこそ、ぜひ手に取ってもらいたい1冊です。
📌 読んだらコメントで教えて!
あなたの「苦手な人」はどんなタイプ?
コメント欄でシェアして、対処法を一緒に見つけましょう!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46872ab9.02c5b347.46872aba.9b903c04/?me_id=1213310&item_id=21207088&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4420%2F9784651204420_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

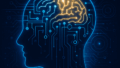
コメント