海外のニュースを見るたびに、
「自分には関係ない」と思ってしまうことはないだろうか。
でも、その“どこか遠い国”に、実は日本が深く関わっているとしたら──?
地理という視点から世界を見てみると、
私たちが思っているよりも、日本はずっと多くの場所に根を張ってきたことに気づく。
🍫ガーナ──“チョコレートの国”に、野口英世がいた

ガーナと聞くと、多くの人はロッテの板チョコを思い浮かべる。
でもその国に、かつて日本の医学者が命をかけて滞在していたことは、あまり知られていない。
野口英世。
黄熱病の治療法を探し求めて、彼がたどり着いたのは西アフリカのこの国だった。
治療法を見つけるまで日本に帰らない──そう決めていた彼は、現地で研究を続け、
やがてその病に倒れ、帰らぬ人となった。
いまもガーナの首都アクラには「野口記念医学研究所」があり、
日本とガーナの縁を静かに語り続けている。
🚢ブラジル──地球の裏側にある“もう一つの日本”

世界で最も多くの日本人のルーツを持つ人が暮らしている国、
それがブラジルだということを、知っている人はどれほどいるだろう。
1908年、たった一隻の船「笠戸丸」に乗って、
貧困と将来の不安から逃れるように海を渡った日本人たち。
その多くは農村出身で、異国の地で人生をやり直そうとしていた。
しかし現実は、甘くなかった。
言葉も文化も通じず、働き方も過酷。
それでも彼らは帰らなかった。
土地に根を張り、家を建て、子を育て、
“日系人”としての誇りを胸に、ブラジルの社会に溶け込んでいった。
今ではその数、200万人を超える。
遠い南米の国で、静かに、そして確かに、“もう一つの日本”が生きている。
イタリア──似ているからこそ、見えてくる“違い”

イタリアと日本は、地図を見れば見るほど似ている。
火山、地震、温泉、細長い国土、海に囲まれた地形。
でも、その上に立つ人々の文化は、驚くほど違う。
イタリアでは、人と人との距離が近い。
街のカフェでは見知らぬ人とも気軽に会話が始まり、
表情豊かに、声を交わす。
一方、日本はどこか静けさを大切にする。
言葉よりも空気を読む、周囲を気にする、そんな文化が根付いている。
それはたぶん、自然災害が多く、共同体の中で助け合って生きてきた島国だからこそ。
だからこそ、「他人を気遣うこと」は、生きるための知恵だったのかもしれない。
似ているからこそ、その“違い”が際立つ。
だからこそ、どこか惹かれてしまう。
日本とイタリアは、“地理的な双子”でありながら、
まったく違う“心の在り方”を育ててきた。
📖この本が見せてくれる“地理”は、生きている
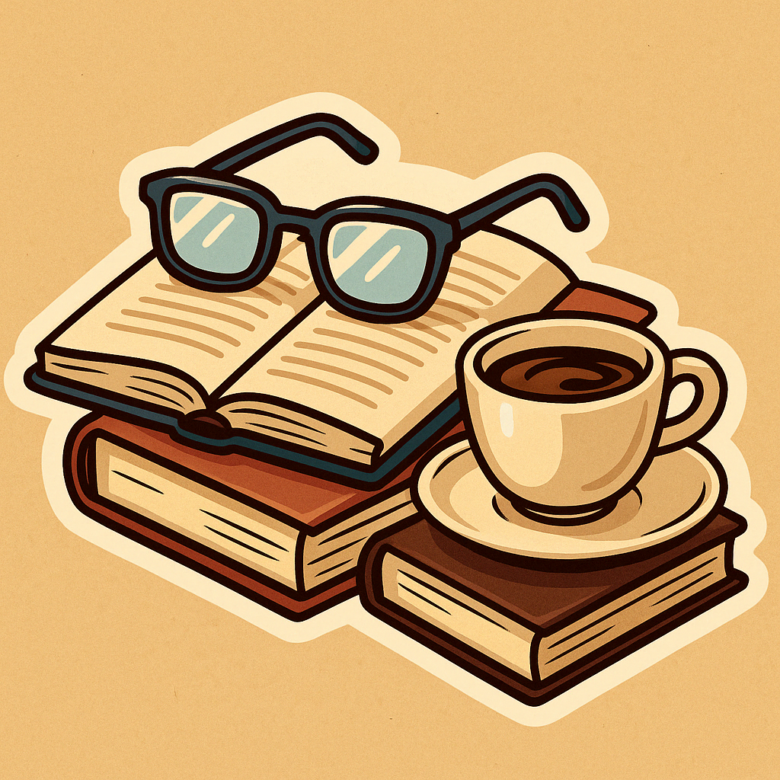
この本は、単なる知識の羅列ではなく、私たちが「世界をどう見つめるか」を問いかけてくれる構成になっている。
アジア、アフリカ、ヨーロッパ、アングロアメリカ、ラテンアメリカ、オセアニア、南極──
地域ごとに章が分かれており、それぞれの土地の自然環境、歴史、民族、経済、そして政治まで幅広く網羅している。
しかも、それぞれの国がどのように発展し、どんな課題を抱えてきたのかが、図解や地図とともに解説されているから、
読みながら自然と「そうだったのか」と膝を打つことも多い。
学校の教科書とはまったく違う、「生きた地理」がそこにある。
✈️あなたも、世界の中の“日本”を探してみませんか?

このブログで紹介したのは、『世界の今がわかる「地理」の本』のほんの一部。
他にもアジア、中東、ヨーロッパ、アフリカ、南極に至るまで、
たくさんの国と地域が、驚くほど“日本”と関わっている。
そしてその関係の中には、
ニュースでは伝わらない人々の人生や、
目に見えない絆が隠れている。
📚この一冊が、きっとあなたの世界を少しだけ広げてくれる。
「地理って、こんなに面白かったんだ」と思える瞬間が、そこにある。
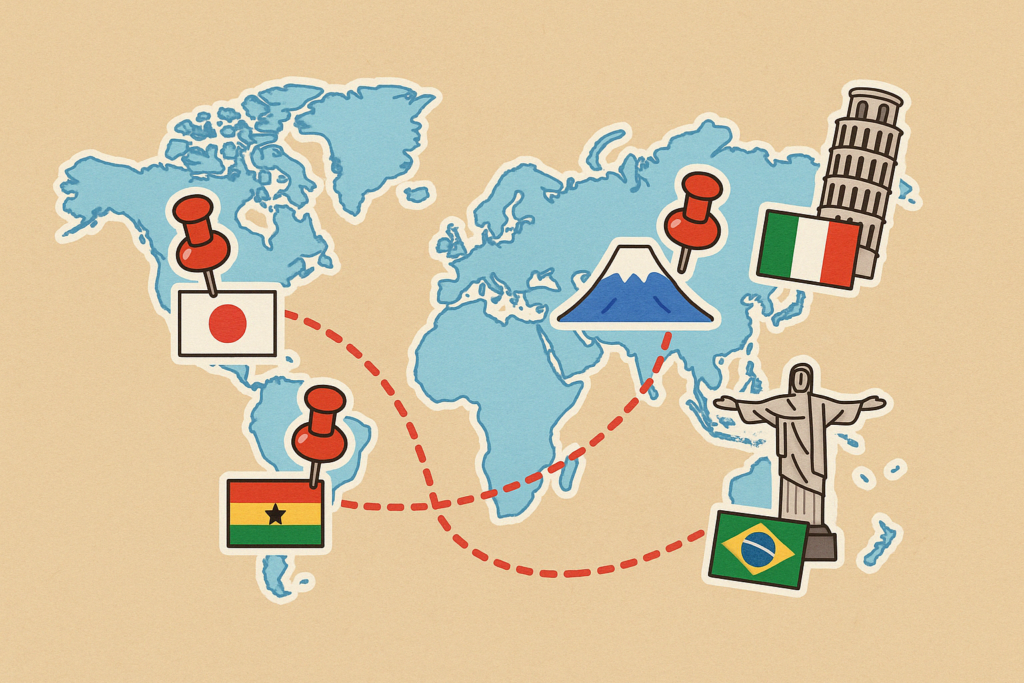
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4726fb75.e2780f34.4726fb76.6c5307c0/?me_id=1276609&item_id=13133380&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbooxstore%2Fcabinet%2F01184%2Fbk4837929516.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


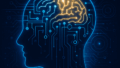
コメント